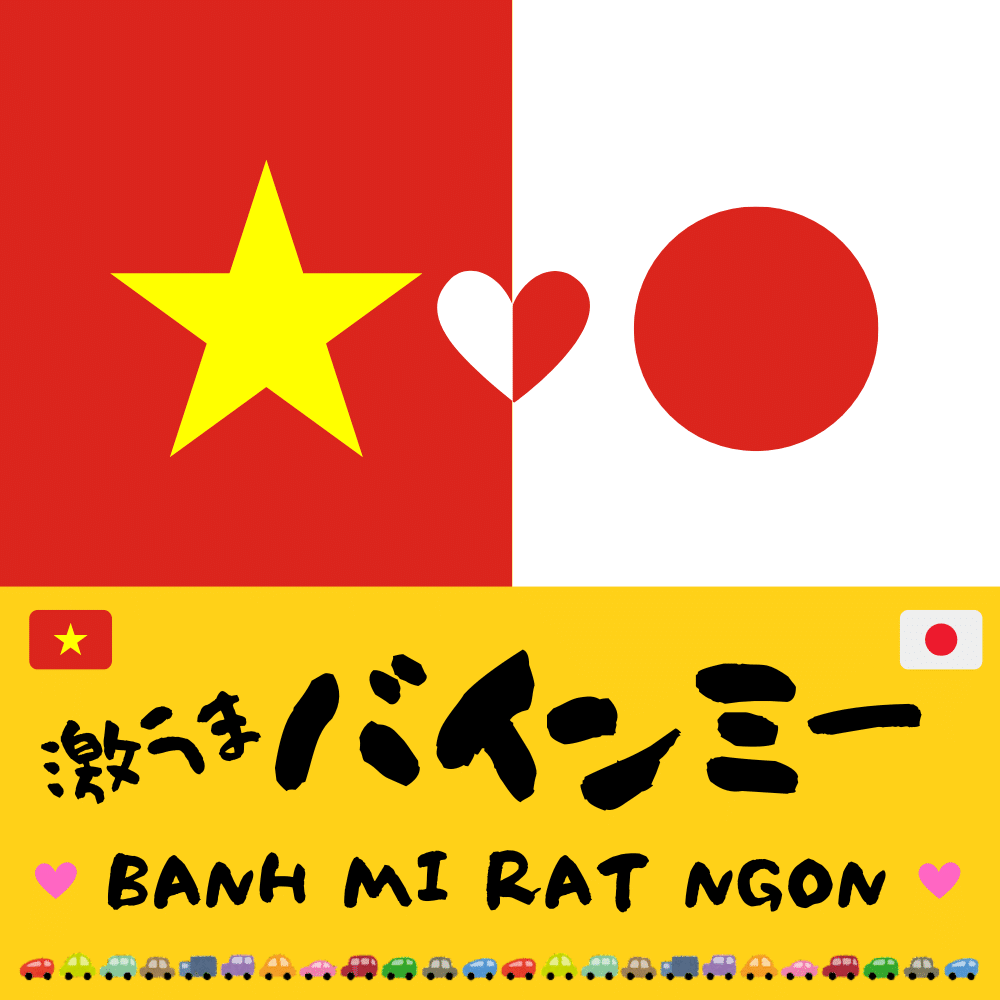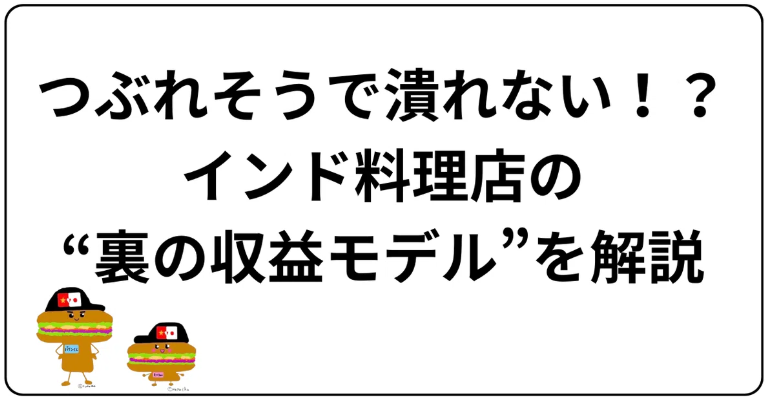みなさんこんにちは!
元気100倍激うまマン!
どうも激うまバインミーです!
というわけで今回は、つぶれそうで潰れない!?インド料理店の“裏の収益モデル”を解説というお話をさせていただければと思います!
ナンって美味しいですよね。。笑
僕はチーズナンが特に好きで、インド料理店があったらついつい行きたくなってしまいます。
今日はそんなインド料理店の裏話をご紹介していきたいと思います!
インド料理のお店って激うまバインミー本店の近くにも2店舗ほぼ同時にオープンしましたが、最近でもどんどん増えてきている気がしますね。
しかもこんなところで売れるの?と思う立地だったり、いつ通ってもお客さんはあまり入っていなかったり、その割に店員さんはいつもたくさんいたりと、本当にやっていけているのかというお店を結構見かけるのではないでしょうか。
そんな状況なのに長年潰れずにずっと営業し続けているお店が多い印象ですね。
ではそれはなぜなのかお話していきます。
まずこのインド料理店のオーナーの多くはネパール人で、ネパール人が日本でお金を稼ぐために経営しているお店になります。
このお金を稼ぐ方法なのですが、やはり普通に飲食店として営業して稼ぐ方法は取っていないことが多いようです。
その仕組みをおおまかに言うと、飲食店経営をしていることを使って、ネパール人労働者のあっせんを行いお金を稼いでいます。
順番に説明しますね。
日本でインド料理のお店をオープンさせると、そのお店の従業員としてネパール人の労働者を呼び寄せることが可能になります。
そのお店の規模などで呼べる人数が増減するのですが、一定上限は決まっております。
大体1店舗で2~3人程度になると思います。
本来なら日本で労働者として在留許可を取得するのは難しいのですが、飲食店があることによって簡単に呼び寄せることが可能になるルートがあるのです。
その労働者を呼び寄せるというハードルを越えられるところに儲ける価値があるのです。
そしてその呼び寄せた人は本来、インド料理屋さんで料理人として働かなくてはいけないのですが、実際は建設業や工場などの別業種へ働きに出ることになります。
そうすることにより、違法ではありますが呼び寄せたネパール人を、建設業や工場の会社に紹介し、紹介料を貰うという流れが生まれます。
なので飲食店のオーナーは、呼び寄せたネパール人の労働者の人数だけ人材紹介料を受け取ることが可能になります。
一昔前は1人あたり100万円以上の報酬を受け取ることも可能だったそうですが、最近だと60万円前後になっているとのことです。
このおかげで飲食店として売り上げが立たなくても、お店の営業を続けることができることになります。
むしろお店の固定費がかからない場所で飲食店をオープンさせた方が、得られる利益が多くなる場合もあるので、こんな場所で?という家賃の低そうな場所でインド料理店が誕生したりすることにつながるみたいです。
また、受入企業からの紹介料だけではなく、建設業などで働く労働者からもお金をもらうこともあるそうです。
労働者としては簡単に日本に来れることと、母国は月給3~4万円ていどなため、母国では稼げない金額を貯金することができるようになることがメリットになります。
飲食店と労働者と日本の受け入れ企業をつなぐブローカーも存在しており、このブローカーが飲食店の開業から人材紹介まで組織的に運営していたりもします。
なのでインド料理店の店員さんたちがあまり上手な日本語を使えなかったり、日本でのノウハウがなさそうに見えても、きれいなお店で、日本語の完璧な看板やメニュー表を作れたり、ややこしい営業許可や各種申請等を行うことができているようです。
もちろん料理人として呼び寄せた人を他業種で働かせるのは違法です。
合法なやり方もなくはないですが、条件はとても厳しいです。
とはいえ見つかりづらいやり方になっているので、ずっとこの経営スタイルで営業を続けていられることになっているみたいです。
以上がインド料理店が不思議と潰れない理由となります。
ちゃんと飲食店として営業できているお店もありますので、すべてがそうと言えませんが、違和感を覚えるようなお店はこのようなカラクリが絡んでいる可能性があるかもしれません。。
そうであってもナンとカレーが美味しいのには変わりありませんけどね。笑
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!