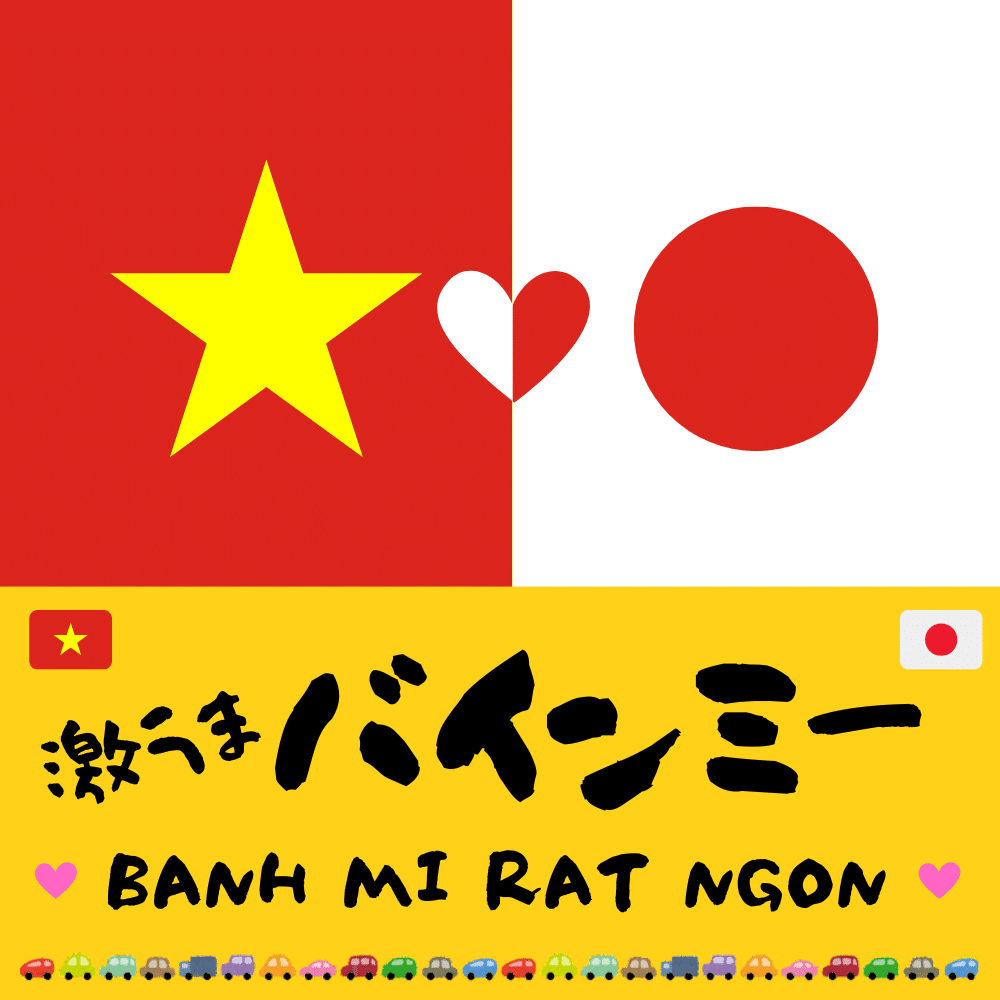みなさんこんにちは!
日常の疑問をブログで解消している激うまバインミーです!
一石二鳥。
というわけで今回は、揚げ物の“ぶくぶく”と“カリカリ”の正体を調べてみた!というお話をさせて頂ければと思います!
日常の風景とまで化していた油で揚げるという行為ですが、よく考えるとなんでぶくぶくしているのか、揚げた後はザクザクになるのかちゃんと理由を知らないなと思いまして調べていきたいなと思います。
もしかしたら当たり前の知識だったらすみません、、笑
まずはぶくぶくする理由から!
ざっくり言うと食材の水分が蒸発しているからというのが要因になります!
油で揚げる時の、油の温度は180度前後ぐらいかと思いますが、水の沸騰して水蒸気に変わる温度は100度です。
なので油の中に入った水分が、油の中で熱せられ水蒸気に変わり、それがあのぶくぶくしている空気になります。
油の沸騰ではなくただ水分が蒸発しているというところですね。
そういえば菜箸を熱した油に入れるとしゅわしゅわしたりしますが、あれも菜箸の中に目に見えない水分が入っているので、その水分が少しづつ蒸発してしゅわしゅわするようですね。
ずっと油に入れているとそのうちカリっと菜箸が揚がるかもしれませんね。笑
ではでは、食材がカリカリになる理由は何だろうというところですね。
ただ水分が抜けただけではカリカリにならないかなという気もしますので気になるところですね。
こちらのざっくりとした要因は、水分の除去&デンプン・たんぱく質の変化というところになるようです。
わかるようでわからない。。
では順番に説明していきたいと思います。
まず食材を入れると先ほどの通り、水分が水蒸気に変わって、食材の表面から水分がなくなっていきます。
食材の中の水分が抜けることによって、元々水分が入っていたところが空洞になります。
これがサクサク感を生む要因となっております。
さらに、その表面にデンプンがある場合、デンプンが溶けて糊のような薄い膜に変化するようです。
デンプンは熱で柔らかくなる性質があり、そこから水分が飛んでいくと乾燥によって固くなるという性質があります。
この性質を活用するために揚げ物には衣をつけて揚げています。
つまり、デンプンを主成分とする小麦粉や片栗粉を衣によく使われているのですね。
そしてたんぱく質も熱によって化学変化が起きて凝固していくことになります。
この凝固がわかりやすいのはたまごですね。
生卵の時はとても柔らかいですが、茹でるとどんどん固くなっていきます。
これによってお肉なども強く引き締まった食感に変わっていくことになります。
これらの変化により、揚げた後にザクザクとした食感を得ることができるようになります。
そう考えると、トンカツなどの揚げ物に使う衣は、小麦粉とたまごとパン粉で、デンプンとたんぱく質の組み合わせになりますね。
ちなみにパン粉は食材の中の水分を守る効果があったり、パン粉によるサクサク感の向上、油を吸いづらくべたつきにくいなどといった効果も得られます。
なので付ける順番も小麦粉➡たまご➡パン粉の順になるのもうなづけますね。
パン粉が外側で守りつつ、小麦粉が全体的に溶けて膜を作り、それらをくっつける接着剤のような役目のたまごがあるという感じですね。
ここまであるように、料理はやっぱり科学の知識がとても必要な分野だと感じます。
ただ美味しいからといった理由だけで食材を選んでいては、つけたい食感だったり、見栄え、形を整えるのも難しくなります。
また、味も化学変化によって変わっていくものでもあるので、それぞれの食材の科学的な知識を増やしていくと、もっと料理も楽しくなってくるのではないでしょうか。
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!