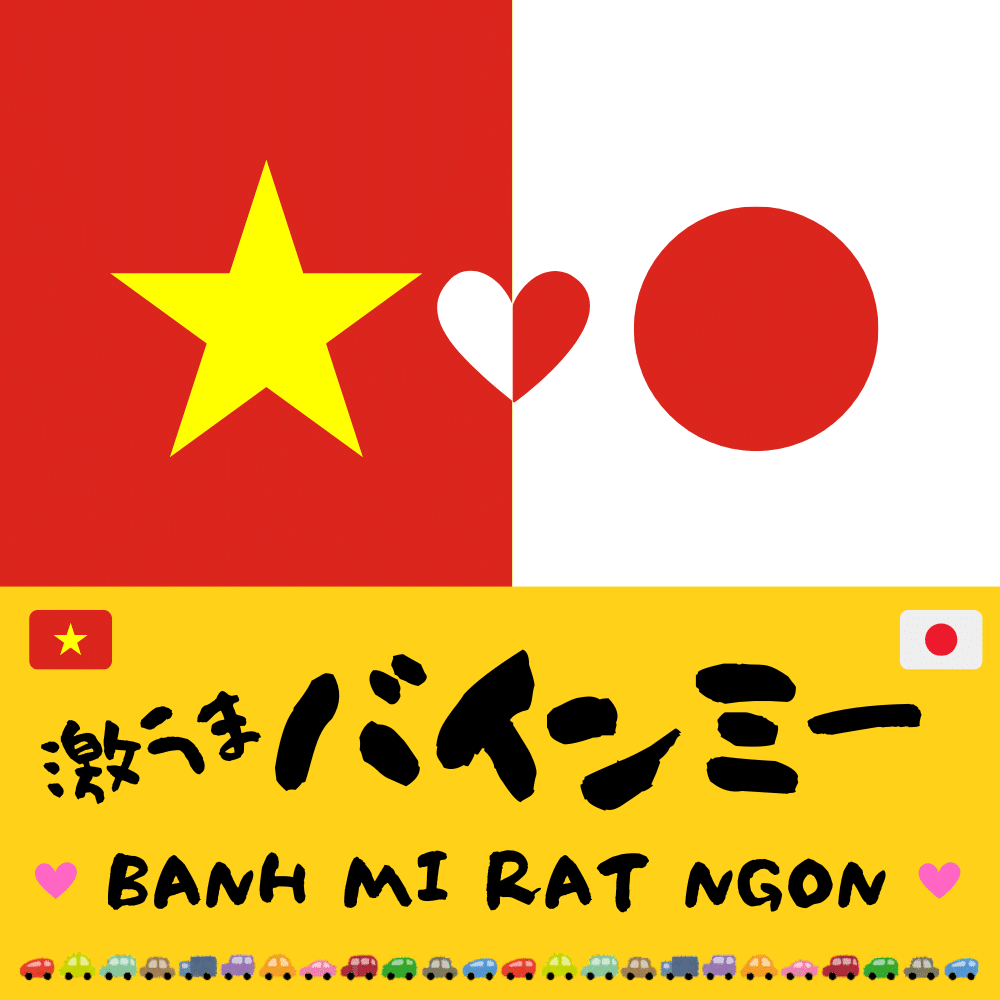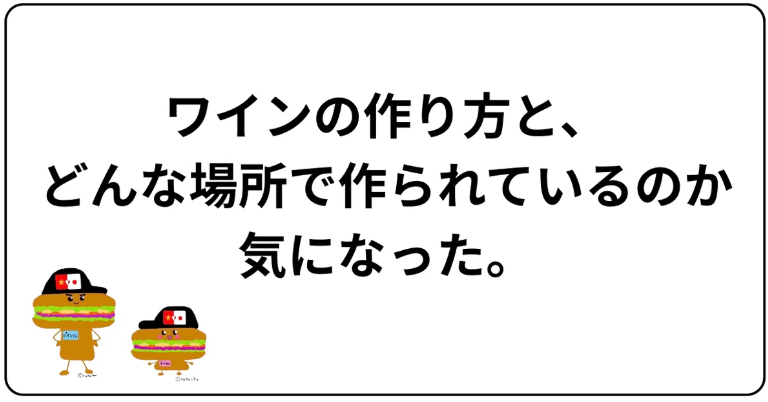みなさんこんにちは!
今年はちゃんと秋があるような気がしている激うまバインミーです!
すごしやすい日が続いてますね。
というわけで今回は、ワインの作り方と、どんな場所で作られているのか気になった。というお話をさせて頂ければと思います!
今回も時々ブログのテーマにしている豆知識的なシリーズで、単純に僕が気になったことを調べてご紹介するというやつでございます!笑
なので僕と一緒にへーって思っていただければ幸いです!
ではでは、ワインの作り方ですが、まずは原料のブドウを選定するところから始まります。
現在はワイン用の品種というのがあり、その品種によって味や香りが違ってくるようです。
代表的なのは、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなどですね。
僕はあまり聞きなじみがないですが、時々ワインの商品名にこれらの品名が使われていたりするので、見覚えがある方もいるのではないでしょうか。
ワインの名前はフランス語でできていることが多いのですが、その名前の中にこれらの品種が使われていることが多く、消費者にとっても好きな品種で選びやすいなどの効果もあるそうです。
ちなみに、ワインの商品名は地域の名前+品種名で表記されることが多いようで、ワインにとって産地と品種というのがとても大事なものだというのがわかります。
ブドウの品種を選んだら加工を行います。
赤ワインの場合はブドウの果汁と皮も一緒に発酵させて作るのですが、白ワインの場合は果汁だけを発酵して作ります。
なので赤ワインの方が渋みや独特な香りがあったりするのですね。
発酵は酵母という、菌を使ってブドウの糖分を分解しアルコールを生み出していきます。
ワイン用のブドウは食用のブドウと比較して甘くなるように品種改良されています。
なのでワインらしいほのかな甘みを残しつつ、高いアルコール度数を出すことができているのですね。
なお、甘いワインを作りたければ、発酵を短くすると糖分が残り甘くすることができるということになります。
発酵が終わると次は熟成に移ります。
熟成は数か月から3年以内が多く、高級品だと10数年~20年以上熟成させることもあるようです。
発酵直後のワインは、発酵によるガスっぽい感じや、味の刺激が強く、香りもきつい状態になっています。
なので、ステンレスのタンクや、オークの木でできた樽などに入れて、先ほど記載した期間、温度や酸素濃度を調整しつつ、太陽光のあたらない、振動も無い場所で定期的にチェックしながら管理することで熟成されます。
熟成が終わるとろ過をして、瓶に詰められ、商品となり出荷されることになります。
以上がワインの加工工程になりますが、これらの工程の中で独自の手法を使い商品の味や香りを生み出していくのです。
さて、ワインを作るのに適した場所になりますが、基本的には温暖な地域が良いとのことです。
年平均12度~22度で、夏は温かく、冬は霜などの冷害がないところですね。
また、日照時間もある程度確保できるところでないとブドウの糖度が上がらなくなってしまうので、周りに何もさえぎらない場所で日が当たるところが理想となります。
さらに、土も水はけの良い土地で、斜面であればなお良いそうです。
赤ワインの場合はこれらに加えて寒暖差がある方が豊かな香りを出すことができるそうです。
白ワインは全体的に涼しめな気候の方が酸味を保持しやすくて向いている土地になるそうです。
世界的にワインづくりで有名な場所はフランスのボルドーやブルゴーニュ、イタリア、チリ、オーストラリアあたりになります。
そしてベトナムもワインを作るのに適した土地がダラットというところにあり、そこの土地名を付けたワインも販売されています。
当店でもダラットのワインをご提供しようと思っていますので、またベトナムのワインも楽しみに来てくださいね!
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!