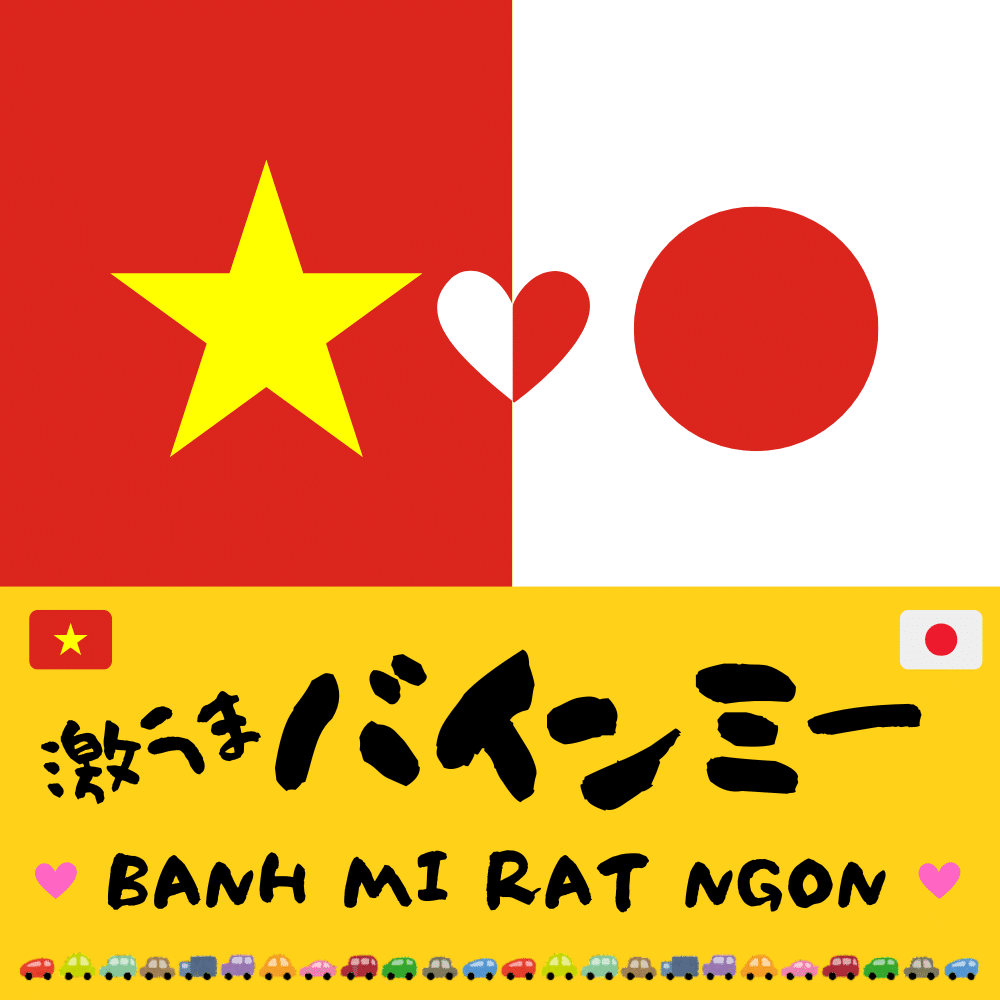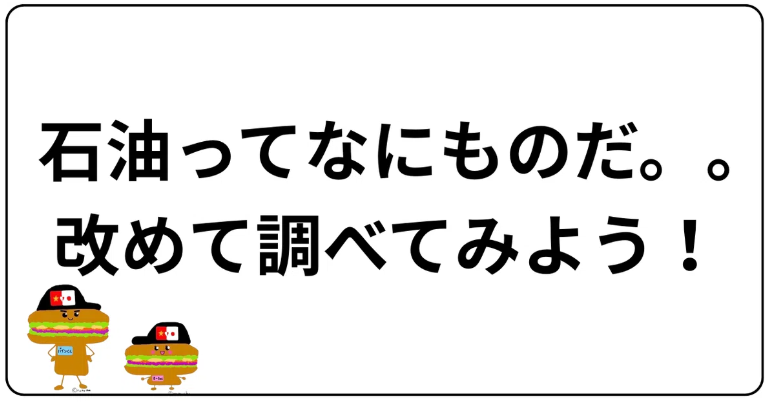みなさんこんにちは!
一日があっという間の激うまバインミーです!
だから一週間もあっという間。。
というわけで今回は、石油ってなにものだ。。改めて調べてみよう!というお話をさせていただければと思います!
石油ってガソリンが一番有名な使われ方なのかなと思いますが、先日のブログにも書いた通り、風邪薬の解熱剤などの成分を作るのにもつかわれていたりするようです。
なので石油っていったい何なんだというのがとても気になりましたので深掘りしてみたいなと思いました。
まずはやはり代表的な使われ方としてガソリン含め燃料が挙げられると思います。
石油の主成分である炭化水素というものが燃えるのです。
炭化水素は炭素、水素、酸素でできているそうなので、何となく燃えそうな気もしますね。笑
燃料としては、ガソリン、軽油、灯油、ジェット燃料、重油など、様々な機械を動かすのに必要な動力源として、各機械にあわせて加工をされつつ使用されています。
また、火力発電用の燃料としても使われており、燃焼効率がとても高く、短時間で高出力であるというのが特徴的です。
続いて、アスファルトにも石油が使われていることをご紹介したいと思います。
アスファルトは道路でよく使われている黒っぽいあれですね。
石油を燃料用に使われた後に残ったものでアスファルトができているようです。
燃料に使われるような成分は石油の中で軽い成分でできており、最後に残るのはアスファルト用に使われる重い成分となっているようです。
アスファルトの持つ沸点が高いという特徴や、常温で固体であったり、高粘性を持っているため、舗装だったり防水としても活躍します。
しかも値段がコンクリートなどに比べても安いことが広く道路などで使われていることとなっております。
そしてそして、一番気になる化学原料としての使われ方が石油の特徴的な使われ方についてお話したいと思います。
化学原料として使われた後の製品としては、プラスチック、繊維、ゴム、洗剤、医薬品などなど、多岐にわたる使われ方をしております。
ざっくり説明すると炭素と水素を基にした有機化合物は、構造を自在に改変できるので、化学製品の基礎原料として使われることができるようです。
そういわれても全然わからないですね。笑
僕も自分で書いておきながら全然わかりません。。笑
なのでめちゃくちゃかみ砕いて説明してみようと思います。
石油はプランクトンなどの死骸が、土の中で数百万年から数千万年かけて、地中の熱と微生物の働きによって作られています。
そのため石油自体の成分はとてもシンプルになっていき、主な成分は炭素と水素がほとんどとなっております。
他にも硫黄や窒素、酸素、金属なども含まれてはいるようですが、割合はとても少ないみたいです。
なので、ほぼ炭素と水素でできたシンプルな構造をしているため、化学反応をさせて、欲しい成分だけを取り出すということが比較的簡単にすることができるみたいです。
とはいえ医薬品やプラスチックになるのはまだ解せないですね。笑
まずプラスチックは、石油を精製して取れる軽めの成分を、約800度の高温で熱すると、エチレンやプロピレンという分子ができるみたいです。
これらの分子をつなぎ合わせていくと、プラスチックの元になるようです。
冷えると固まり、高い粘性で弾力も持つという性質が得られます。
繊維は石油を精製したものから取れる成分をさらに分解し、そこに化学反応を起こし酸とアルコールをくっつけ、それらをたくさん集めてつなぎ合わせていくと糸が出来上がっていくことになるみたいです。
ゴムも同様に分解させて取った成分をつなぎ合わせたり、硫黄を混ぜ合わせることによって弾力性を強化させることで作られて行きます。
洗剤は石油から取れる油っぽい分子に、水とくっつきやすい分子をくっつけて、油にも水にもくっつきやすい分子というのを作ります。
そうすると油汚れに洗剤をつけて水を流すだけできれいになるという効果が得られるようになるみたいです。
医薬品は、石油の中にある単純な分子に、酸素や窒素などを加えていき、機能を持つ分子を作っていきます。
炭素と水素からできている石油なので、体に入れても大丈夫そうなのは理解できますね。
機能を持つ分子というのは、元々知られている熱や咳などに効く分子の形になるように、分子を作り上げていき機能を持たせるようにしているようです。
なので石油から取れる成分は、色んな効果を持たせるための骨組みに使っているということになりますね。
石油って燃えるこわいものっていうイメージで、特に医薬品にも使われていると言われるとびっくりしますが、こうやって見ると安全そうなことや、人類の科学力の凄さが見えてきた気がします。
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!