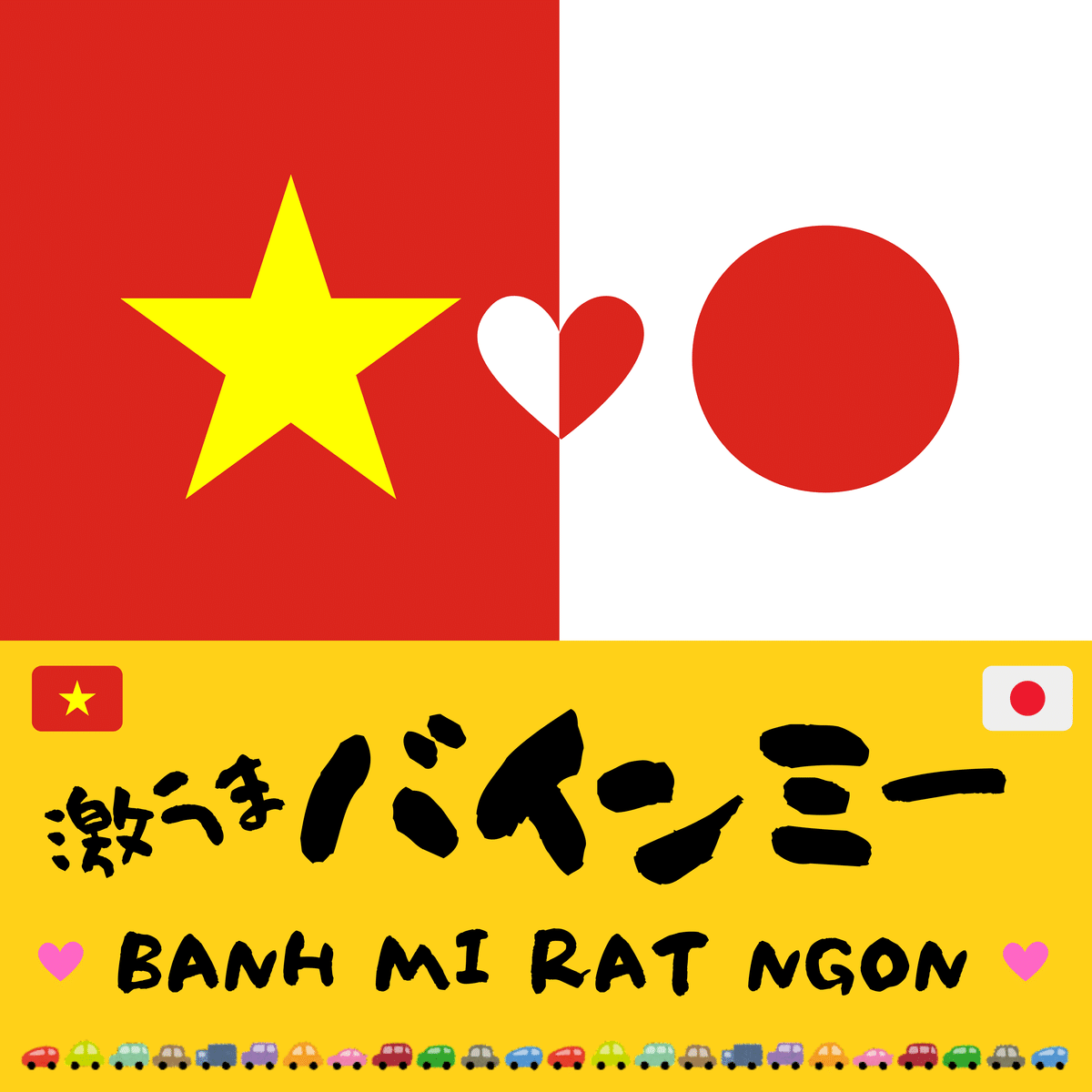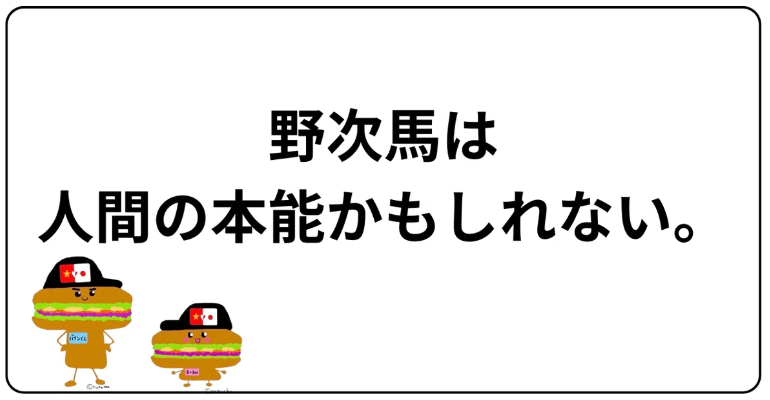みなさんこんにちは!
馬にハマっている激うまバインミーです!
ひひーん
というわけで今回は、野次馬は人間の本能かもしれない。というお話をさせて頂ければと思います!
昨日は馬車馬が気になったので調べてみた回になりましたが、今回は野次馬について調べていきたいと思っております。笑
とはいえ言葉について解説するだけだと1行とかで終わってしまうので、そこは何とか考えながらお話していかなければなと思っております。笑
まず野次馬の意味ですが、何かの事件や事故が起きたときに見物しに集まる人のことを言いますね。
ちょっと否定的な、興味だけで首を突っ込む人のような意味があります。
そんな野次馬ですが、野次と馬を組み合わせてできた言葉のようです。
野次というのもよく聞きますが、やかましく冷やかす、からかうというような意味があります。
江戸時代の芝居や相撲、祭りなどの中で使われるようになった言葉のようで、野は外という意味と近く、一般の場よりも外側、野外や屋外の場所を指しています。
次という漢字は、声を出す行為を指しているという説があります。
芝居や相撲を見ている観客や、その外にいるような人たちが掛け声を挙げていることを野次と呼んでいたということですね。
ただ古語や俗語などから派生してできたという説もあるようですので、これだけが正しいとは言い切れないようです。
ではでは、そんな野次に馬がついた理由についてですが、一つは見物人が馬の群れのように押し寄せてきているという比喩表現が含まれています。
馬は人や群れ、騒ぎを面白がって追いかけるという習性があるため、野次をする人たちが押し寄せているという表現をするために馬を使うようになりました。
もう一つが、落ち着きなく動き回ったり、好奇心の強い生き物というイメージが馬にあったため、騒ぎに集まるような動き回ったり、好奇心のある人たちの比喩としても馬を使われることになったようです。
さらに、「〇〇馬」という表現が俗語で「~をする人」という意味で、軽くからかう言い方として使われていたそうです。
けち馬、冷やかし馬という表現が一時的に使われていました。
これらを総合して野次馬という表現が定着するようになっていったみたいですね。
ちなみに他の説だと、おやじ馬という言葉から派生してやじ馬に変わったという説もあるみたいです。
おやじ馬は年老いた馬という意味で、先頭に立たず、何かに従うだけの馬という意味がありました。
そこから、役に立たないくせに、物知りを装うだけの人を比喩表現するときに、おやじ馬が使われるようになり、その意味がそのまま残りやじ馬に変化していったという説となります。
馬は昔から生活の一部にとけこんでいた生き物ですので、何かの言葉に入りやすいというのはイメージできますね。
そこから〇〇馬という言葉がたくさん増えていったのも想像がしやすいです。
とはいえ現代で残っているのは野次馬だけのようです。
つまり、現代になって馬と触れ合っていない人たちしかいないような社会でも、野次馬という言葉だけ根強く残っているのは、野次馬をする行為が今も昔も全く変わらずに、人間の本能のように残っているからかなと感じます。笑
となると、どこかしこにも集まる野次馬の方々は、人間の本能として組み込まれた性質なので、止めようがないということになりそうです。
なので何か事件が起きてスマホで撮影する人だかりができるのは自然の摂理なので、これをどう減らすかと考えるより、この人たちありきでどう立ち回るかという方向で考えていくべきなのかなという気もしました。
AEDや救急車が必要な場面で、野次馬でない人を見抜く方法とか、手助けしてくれそうな人を選ぶ方法とか、逆に野次馬の中でどうやって手助けするのか、たくさんの人に見られながらでも冷静に行動できる方法とかを学んだ方が身になりそうな気がします。
僕もただの野次馬にならないように気を付けないとなと思います。。
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!